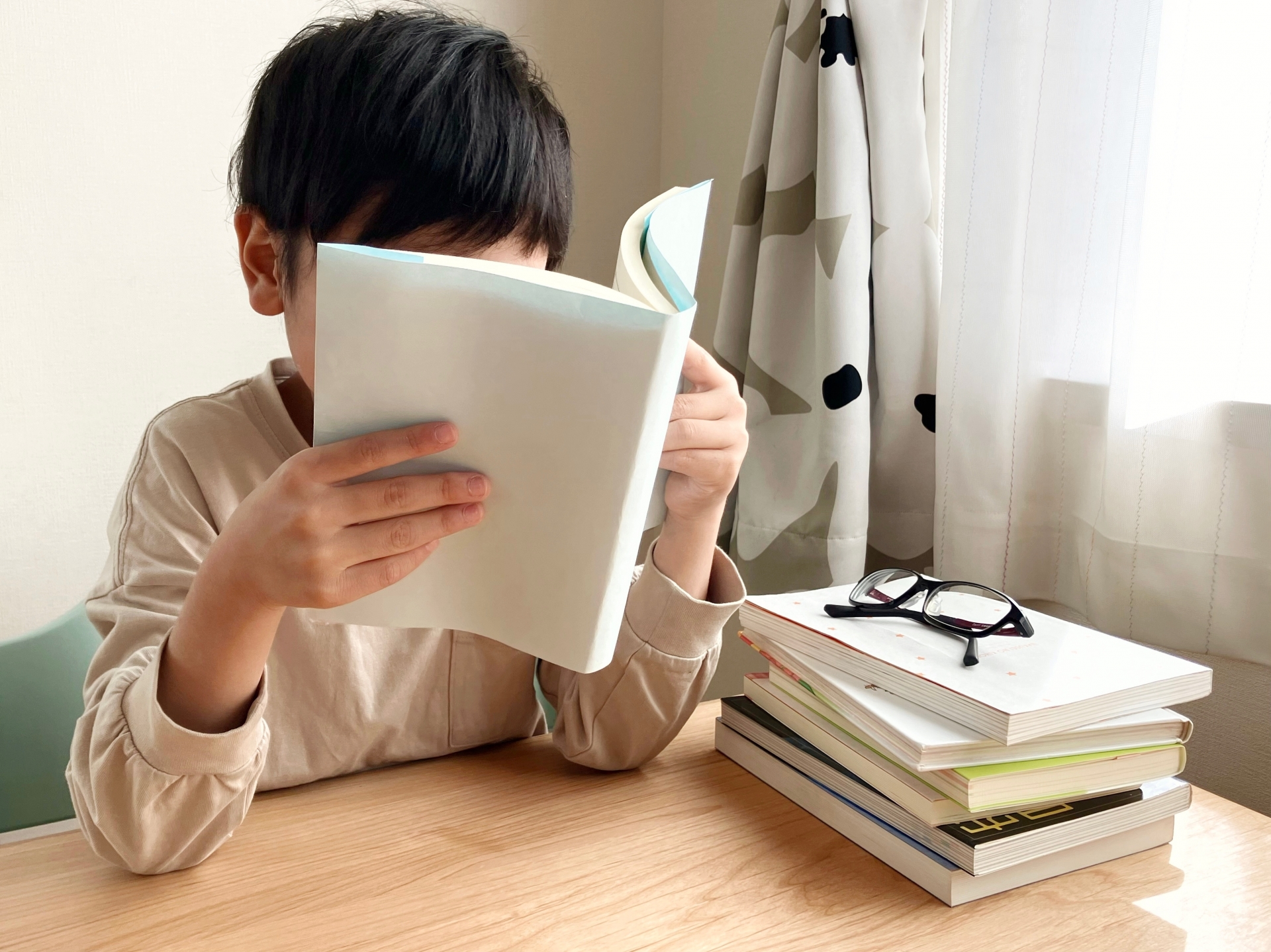ブログ
【中学受験国語】生徒との対話で印象的だった瞬間:自己分析力が示す真の成長
国語2025.10.02
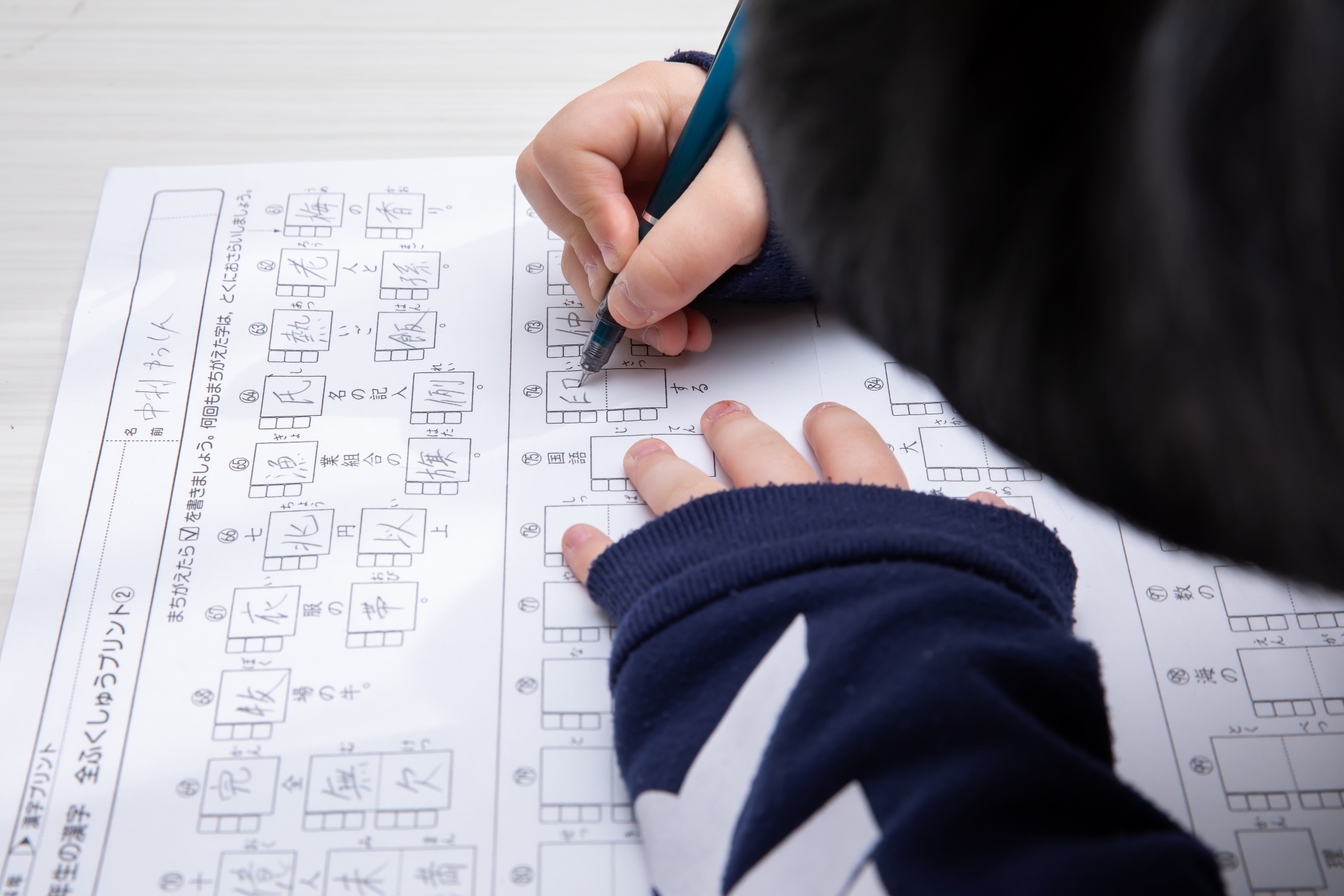
講師として活動しておりますと、生徒の成長を目の当たりにする瞬間に立ち会うことがあります。それは必ずしもテストの点数が上がった時だけではありません。むしろ、生徒自身が自分の間違いを深く理解した瞬間にこそ、本当の成長を感じることがあります。
ある日の対話
この瞬間、私は心から感動しました。なぜなら、この生徒は単に「間違えた」という事実を認識しているだけでなく、なぜ間違えたのか、どこがズレていたのかを正確に言語化できているからです。
これって本当にすごい成長
「どう感じたか」と「なぜそうなったか」の違い
国語の記述問題では、問われている内容を正確に理解することが何よりも重要です。しかし、多くの生徒がこの二つを混同してしまいます。
例えば、「主人公はこの出来事にどう感じましたか?」という問いに対して:
→ 原因(なぜ)を説明している
→ 感情(どう)を直接的に表現している
なぜこの自己分析が「すごい」のか
自分の思考プロセスを客観的に見る力、つまり「メタ認知能力」が育っている証拠です。これは学習において最も重要な能力の一つと言われています。
多くの生徒は、テストで間違えたとき「わからなかった」「難しかった」という感想で終わってしまいます。しかし、この生徒のように「問題の要求を取り違えた」と具体的に分析できることは、次につながる大きな一歩なのです。
答案を見直す力が学力を伸ばす
答案を見直す力とは、例えば単に計算ミスを探すことではありません。自分の思考の癖や勘違いのパターンを発見する力です。
この力を身につけた生徒は、同じ間違いを繰り返さなくなります。なぜなら、表面的な「正解・不正解」だけでなく、間違いの根本原因を理解しているからです。
自己分析力を育てる3つのステップ
講師として感じること
生徒が自分の間違いをこれほど明確に分析できた瞬間、私は「もう大丈夫だ」と感じます。なぜなら、自己修正能力を身につけたということだからです。
これからも間違いはあるでしょう。しかし、その度に自分で原因を特定し、改善策を考えられる。そんな生徒は、講師がいなくても、自分の力で成長し続けることができます。
テストの点数は確かに重要な指標です。しかし、それ以上に大切なのは、自分の学びをコントロールする力を身につけることではないでしょうか。
すべての学習者へ
もしあなたが今、テストの結果に落ち込んでいるなら、一度立ち止まって考えてみてください。
「どこで間違えたのか?」
「なぜ間違えたのか?」
「次はどうすればいいのか?」
この問いかけができるなら、あなたはすでに成長への道を歩み始めています。点数だけでは測れない、本当の学力が育ちつつあるのです。
自分のミスを客観視し、言葉にできること。
それこそが、継続的な成長を可能にする最も重要な力です。
✨ 間違いは、成長のチャンス。