ブログ
【中学受験国語】4・5年生が読解の壁を越えるために:今こそ習慣づけの時期
国語2025.11.10
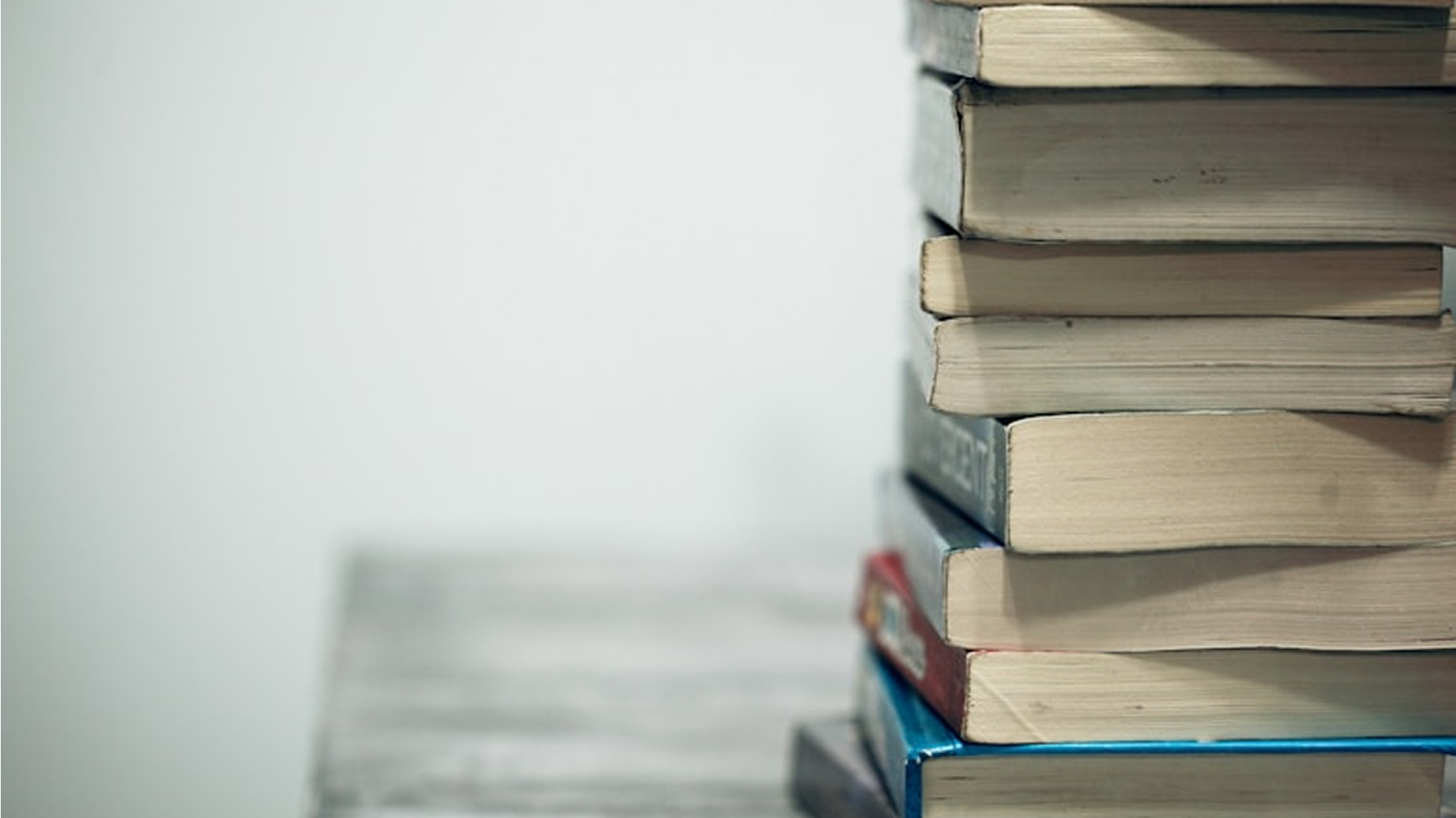
4・5年生が読解の壁を越えるために:今こそ習慣づけの時期
中学受験を目指すお子さんをお持ちのご家庭にとって、4年生、5年生は大きな転換期です。特に国語の読解において、この時期に訪れる変化は見逃せません。
4・5年生で訪れる「読解の壁」
この時期から、どの塾でも読解の授業で扱う文章の難しさがグンと上がります。
サピックスに通われているご家庭なら、B授業のテキストを思い浮かべていただくとわかりやすいでしょう。4年生の前半までは比較的取り組みやすかった文章が、この時期を境に急に手応えが変わってきます。
何が変わるのでしょうか?主に次の2点です。
文章の長さとテーマの多様化
文章が長くなる
長文を最後まで集中して読み切る体力が必要になってきます。途中で集中力が切れてしまうと、設問に答えられなくなってしまうのです。
テーマが多岐にわたる
低学年では、子どもにとって身近な題材が中心でした。しかし4・5年生になると、環境問題、戦争、家族の形、人生観など、抽象的で深いテーマの文章が増えてきます。単に文字を追うだけでなく、背景知識や人生経験も必要になってくるのです。
だからこそ、復習が何より大切
文章が難しくなる今だからこそ、授業の復習をしっかりしていきましょう。
「授業で一度やったから大丈夫」と思いがちですが、それは大きな誤解です。難しい文章こそ、繰り返し向き合うことで理解が深まっていきます。
必ずやるべき3つの復習
復習には様々な方法がありますが、特に次の3つはマストです。
1. 音読
授業で扱った文章を、声に出して読み直しましょう。黙読では気づかなかった文章のリズムや、登場人物の感情が見えてきます。
音読することで、文章の構造が頭に入りやすくなり、読むスピードも自然と上がっていきます。
2. 本文中の言葉の意味調べ
授業中に「わからないな」と思った言葉、先生が説明してくれた言葉を、改めて辞書で調べ直しましょう。
この時期から語彙力の差が、読解力の差に直結してきます。一つひとつの言葉を丁寧に理解していくことが、後々大きな力になります。
「この言葉、こういう意味だったんだ」という発見が積み重なることで、次に同じような文章に出会った時、スムーズに理解できるようになるのです。
3. 解き直し
間違えた問題はもちろん、正解した問題も含めて、もう一度解いてみましょう。
「なぜこの答えになるのか」を、本文の根拠を示しながら説明できるようになることが目標です。授業で先生が説明してくれた解法を、自分の言葉で再現できるかチェックしてみてください。
ここで曖昧なまま進んでしまうと、6年生になった時に基礎力不足で苦労することになります。
忙しい毎日でも、習慣づけを
他の教科の宿題もあり、習い事もあり、お子さんもご家庭もお忙しいことと思います。
でも、ここで国語の学習習慣をつけておくことが、6年生になってからの飛躍に繋がります。
6年生になると、過去問演習が始まり、時間的な余裕がどんどんなくなっていきます。その時になって「国語の基礎が固まっていない」と気づいても、立て直すのは非常に困難です。
逆に、4・5年生のうちに:
- 長い文章を最後まで読み切る集中力
- 抽象的なテーマを理解する思考力
- 語彙力と読解の基礎体力
- 毎日コツコツ復習する習慣
これらを身につけておけば、6年生での伸びが全く違ってきます。
毎日少しずつ、確実に
完璧を目指す必要はありません。毎日15分でも20分でも、国語の復習に時間を使うこと。その積み重ねこそが、後々大きな差となって現れます。
お子さん一人では難しい場合は、最初は保護者の方が寄り添ってあげてください。「一緒に音読しよう」「この言葉、どういう意味だったかな?」と声をかけるだけでも、お子さんのモチベーションは変わります。
まとめ:今が踏ん張りどき
4・5年生は、読解力を大きく伸ばせる時期であると同時に、差がつき始める時期でもあります。
- 文章の難易度が上がる転換期
- 復習(音読・意味調べ・解き直し)がマスト
- 今の学習習慣が6年生での飛躍につながる
- 完璧でなくても、毎日少しずつ継続することが大切
頑張っていきましょう。
お子さんの国語学習について、何かご不明な点やご質問がございましたら、いつでもご連絡くださいませ。一緒にお子さんの成長を支えていきましょう。